/
般若心経を読む (神谷湛然)/
般若心経を解する
湛然解釈
はじめに
般若心経ほど親しまれ、読まれているお経はないいだろう。いろいろな解釈本が古来 から出ているが、わかったような、わからないような、なにかもやもやした気持ちがするのは私だけだろうか。その原因は、(空)(無)のとらえかたのように思われる。自分の身にひきつけて、生々しい実践体験、
様々な人たちの跡かたを辿りつつ、読んでいかなければならないように思う。
魔訶般若波羅密多心経とは
(魔訶)とは大と訳されるが、想像できないほとの無限大、すなわち宇宙一杯ということだ。概念ではわかったような気分になるが、広大無辺としかいいようがない。(般若)は智慧と訳されるが、意識分別のように思われてよくない。私的にいえば、ありように一枚になることと解する。竹ぼうきを持って掃くとき、竹ぼうきとともに自分も掃いている。竹ぼうきが左に掃けば自分も左に掃き、右に掃けば自分も右に掃く。石垣の合間に生えている名も知らぬ草の葉を手にとって見れば、私が葉っぱを見ているのではなくて私は葉っぱであり葉っぱは私である。葉っぱそのものがなんの分別もなく概念もなくストレートに目に飛び込んでくる。はりきゅう師 でもある私は、人の体にはりを打つ時、はりとともに私もその体の中にもぐりこんでいく。それはそれだけであり、あれはあれだけである。見るままに見るというなり、聞くままに聞くというなり、である。(波羅密多)は到彼岸と訳される。真実にいたる手立てとでも言おうか。(心)とは髄、エッセンスである。(経)は教えということだ。
観自在菩薩とは
唐の玄奘三蔵はクマラジュが観世音菩薩と漢訳したのを改めて観自在菩薩と訳し直した。法華経に観世音菩薩普門品がる。これもクマラジュが漢訳したものであるが、意味的には観自在菩薩普門品とすべきだと思う。その場その場に応じて現れはたらき活動するするいきいきとした有様を説く教えだからである。十一面は千面万面無限面であり、千手は万手億手無限数手であるその時その場に応じて融通無礙・自由自在にはたらく。まさに生命そのものではないか。その生命を生きている人がその生命そのものに生きようとして修行している人、他ならぬあなたなのだ。そういう生命を生きようとして、なにのはからいもなく単々と行じる。これを(深般若波羅密多)という。それを行じているなかに、すべての物がすべての思い考え概念意識なにもかもがコリッとしたものはなく無為転変としていきいきとあるがままにあるだけである。これを(空)として自覚させられた。(照見)はかなたのほうから、つまり広大無辺な周りから照らし出されて知らされたという意味である。単々と為すなかで露わ出る有りようである。(空と聞くと、(むなしい)とか(うつろ)とか把えてしまうのは俗的意味に溺れてしまうからであろうか。
色即是空 空即是色
(色不異空 空不異色 色即是空 空即是色)という件りがあるが、サンスクリット原文ではその前に(色不色 空不空)という文があるという。ダイナミックな生命現象を表現しようとしたものだと私は思う。山は山ではない、山ではないがそれでも山である。尖った山、丸井山、高原のような山、天保山みたいな高さ4.53メートルの人工的に作られた築山・・・。同じ山でも刻々と風景を変え、見る人によっても、鳥獣虫、様々な草木によっても違う。水は人は水と見るも、魚はすみかとみなし、餓鬼は火炎と見、天女は翡翠と見る。(一水四見)である。水自身も様々に姿を帰る。河になり海になり、蒸気となっていろいろな雲となり、雨雪霰氷となって地上に落下する。はたまた生物の中にたくさん溜め込まれて生命を支えている。電気分解すると酸素と水素の気体になる。その水素・酸素もさらに分解すれば電子・陽子・中性子、陽子・中性子はさらに3つのクォークという素粒子があるという。なお電子はレフトんという素粒子だという。そして宇宙には6種のクォークと6種のレフトん(電子の仲間)、他に光子などの5種の素粒子があって、全部で17種類(標準理論に入っていない重力子をいれると18種類)の素粒子で成り立っているという。そうではなくて、もっと多く存在し、宇宙の大部分を占める暗黒物質(ダークマター)の実体は未解明であるといううう科学者がいる。物質の根本単位への追及はまだ終わっていないというのである(様々な素粒子は見え方が違っているだけであって、超弦という単一のごく小さなヒモで成り立っているのではないかと考えている人がいる)。私たち自身も何者かと考え、どこから来てどこへ行くのか。はっきりしているのはただ今ここにある私だけである。一瞬一瞬の刻々と変わる私の今かぎりがある。その今をつかまえようとしたらその今はもうない。限りなき宇宙生命の一瞬の現象、夜空に輝きう星々と同じではなかろうか。ありがたき命とは思わずにいられないではないか。
是諸法空相 不生不滅 不垢不浄 不増不減
(空)はそういう豊饒な生命のダイナミックさを表現したものであり、一瞬一瞬の輝きであり、それ限りだからこそ、生じてなくなるという時間経過のあるものではなく、価値判断もなく量的にも質的にも増えもしないし減りもしない。菊は菊であり、菊以上でも菊以下でもない。どこからか生じて菊となりのちに枯れおわるというものではない。ただ今現前している菊そのもので完結している。それをつかまえようとしたらもうすでにそれは過ぎてしまっている。そういう今今を新繊維活動している生命、一切の万物を(不生不滅)と心得るべきである。
再び(不生不滅)を考える
人々は、物事にははじまりがありおわりがあると考える。父母の和合によって私は生まれ、成長し老い病自己災害戦争などによって死亡しという形で一生を終えるという。世間的には当たり前である。しかし、宇宙生命のありようを説く仏法からすれば、それはまちがいだと諭す。やすみなく呼吸し心臓を動かし、水や食物の摂取・糞尿の排泄を絶えず行っている。刻々と寝ている間も新陳代謝し、意識思いも内外に影響されてコロコロ変化する。とっかえひっかえしながら絶えず私を否定し新しく作りまた間髪入れずに壊して亦作り直す。小倉道雄さんの(本日ただいま誕生)である。また、(私)たる元は父母というが、そのさらに元はと辿っていくと700万年前のアフリカ東部にいくといわれる。さらにはるか先にいくと138億年前のビッグバンにいきつくという。さらにその元があるのではないかと推察する科学者がいる。無からはじまったのではなくビッグバンの前にごく小さな宇宙が生まれては消えており、その一つがなんらかの原因によって消えずに成長したのが今の宇宙だという説がある。ある説では、生まれたての宇宙は11次元の世界であり、成長するに従って三次元の空間と時間の一次元からなる世界に整理されたという。まだ宇宙のはじまりは依然として謎に包まれているという。死滅のほうを辿っていくと、40億年かのちに地球は超高温化して融解して生物は全滅し、約75億年後には膨張して赤色巨星となった太陽に呑みこまれ、百億年後には太陽は超新星爆発して大量の光とガス・物質を宇宙空間にばらまいて、また新しい星の生成材料を与えると、宇宙物理学はいう。そうではなくて、赤色巨星ののちに大量のガスを宇宙空間に放出しながら収縮して地球程度の大きさの高密度の白色矮星となり、想像もできないはるかのちに黒色矮星という燃えカスとなって太陽は終わると考える科学者もいる。その矮星も超新星爆発して宇宙空間にばらまかれると最新のある学説はいう。私たちは宇宙のかなたからやってき、宇宙のかなたへ去っていく。なにをもって(生)といい、なにをもって(死)
といえようか。世間で暮らす上で、とりあえずここからを(生)とし、(生)の尽きたと思われるところを(死)とみなすということである。
是故空中 無色・・・
ここから心経は、空の中にあるが故に、ということで(無)を何度も用いて一切を(無)と規定する。この(無)も(空)と同様に、‘有不有 無不無 有不異無 無不異有 有即是無 無即是有’というところの(無)でなければならないはずである。あらゆる存在現象は、はまりにも動的で無限に転変流転している様を言葉で表そうとしたらどうしても二律背反的な使い方になってしまう。(空)だからこそ、無数の存在、豊饒な精神の働き、豊かな感覚世界・精神世界があるのだと私は聞こえる。概念とか教義、宗趣に真実があるのではなく、この生々しい今を生きろ、と叱咤激励しているように思うのである。水上勉は(般若心経を読む)において、心経はなんと冷たくて高遠だろうと嘆息している。心経は地獄でのたうち回る凡夫のことなんかわかっちゃいないと憤慨している。(無)を全否定と解するならば当然である。一本のコスモスの花に高原のさわやかな秋を思う人、火葬場裏のコスモスを思い出して涙ぐむ人、ふるさとを思い出して懐かしむ人、暑い夏が終わったなあとホッとする人・・・。いろいろなコスモスが現前している。コスモス自体も刻々と変化する。ただいまそれがそれとして無限に広がっている。
(苦)を考える
人生は苦である、と釈尊は説いた。諸行は常であり、諸々の法は無我である。にもかかわらず執着して苦悩する。なぜ執着するのか。常なるものを夢見、実体があると思い違いするからだと仏はいう。落ち込むときは落ち込む。ひもじい時はひもじい。痛い時は痛い。うれしいかなしいはうれしいかなしい。そういう感覚作用精神作用はその時その場でおわり。車窓の景色が過ぎ去るがごとしである。これが執着すると根となってあらぬ悩みを作り出し、殺人や戦争まで発展することがある。生命が生命としてとして、空が空として現前するならば、のたうち回るのもよし、よろこび悲しむのもよし、うまいまずいいたい気持ちいいと感じるのもよし、どう生きるのもよし、融通無礙自由自在、日日新しく新しく生きたいものである。
ぎゃていぎゃてい・・・
心経の最後は梵語である。和訳は次の通りだという。
行こう 行こう、彼岸に行こう、完全なる彼岸に行こう、悟りヨ、さいわいあれ。
彼岸と聞くと、悟りの世界・あちらの世界と思いがちだ。それに対して、こちらの世界を此岸といって私たちの住む俗世間と思う人が多いだろう。まったくお盆・彼岸会の弊害かもしれない。彼岸は実は私たちの足元にあるのだ。彼岸を浄土といってもよい。ここを浄土にするのか地獄にするのか私たち次第だということを法華経方便品は説いている。この世界を花園楽園とみるのか、阿鼻叫喚の地獄とみるのか、見方次第だと問いかけていると思うのだ。
最後に、心経の最後にある梵文を美しい日本語に意訳してみたい。
渓の声 山の色も みなながら わが釈迦牟尼の 声とすがたと
道元禅師の道歌である。
2022年12月01日記

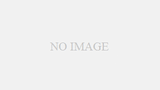
コメント