/ 68.八紘一宇について
八紘一宇という言葉が国会で話題になったことがあった。
2015年3月に、三原ジュンコ参議院議員が、神武が唱えたとされる八紘一宇を話題に出して当時の麻生太郎財務相と安倍晋三首相に質問したことがあった。世界が一家族として睦まじく助け合うという、この理念を政府的合意文書みたいなものを作って世界に提案しないのかというものだった。
日本書紀によれば、神武が南九州から東征して大和の橿原宮(かしはらのみや)で即位する時、‘八紘をおおひて宇(いえ)とせむ’と言ったとされる。つまり、天下をまとめて支配しようと思うということである。
日本書紀が世に出たのは奈良時代初頭の8世紀初めといわれているが、八紘云々はその日本書紀よりはるか以前に、中国の「史記」(前1世紀初頭)から「明史」(18世紀前半)に至るまで漢族で一貫して用いられたと平勢隆郎は指摘している。また、平勢は、‘八紘’は野蛮なところとみなしている周辺地域を除いた自らの居住地を指すという。そしてその居住地は時代とともに拡大していった。
以上のことを踏まえるならば、神武の言う‘八紘’は、古事記のいう八島、すなわち、淡路島・四国・九州・佐渡・本州・隠岐・対馬・壱岐をいうと理解するのが自然ではないかと思う。しかし、神武がそんなことを本当に言ったのか、そもそも神武なるものが存在したのか、などなど疑問が尽きないが、問題は、当時日本が大東亜戦争と読んだアジア・太平洋戦争中に、もてはやされた‘八紘一宇’の中身である。
辻田真佐憲の『「戦前」の正体』によれば、全世界を天皇の元におく、という意味に転化されたという。戦時中の日本は、中国東北の満州や内モンゴル、そして中国本土をも実質支配し、朝鮮・台湾・ひ・フィリピン・インドネシア・インドシナ半島・シンガポール・マレーシア・ビルマ(ミャンマー)・ニューギニア、そして北太平洋のアリューシャン諸島・メラネシアやミクロネシアの南太平洋の多くの諸島まで版図を拡げていった。日本は絶頂期には、東アジア、東南アジア、ポリネシアを除いた太平洋一帯を支配下に置くことができたのだった。支配下で行われたのが、日本との同化政策と天皇を頂点とする国体思想の注入だった。朝鮮人や中国人に対する差別は特にひどかったようだ。‘そんなことはバカでもチョンでもできる’という言い回しが今でも使われることがある。その中の‘チョン’は‘チョングオレン’の中国人のことであり、また、‘チョソンサラム’の朝鮮人のこととも解されていると私は見る。民族差別の具現した一例だといえよう。
八紘一宇の一宇は、それぞれの国の言語や文化・人種や政治体制などの違いを認め合いながら加盟している国連とは全く違うものであり、まさしく、独裁者による全世界の一元支配を意味するものだと言わざるを得ないだろう。
三原ジュンコ議員が言う、お互いに睦まじく助け合う世界平和を実現したいのであれば、国連のような世界機関の充実と強化を図るよう働きかけることこそが本筋ではないかと思うばかりだ。
私は、一仏教者として、特に戦時中に高徳といわれた仏教者でさえ、八紘一宇・教育勅語・皇道宗教に無批判に受容するだけでなく、積極的にそれらを先頭に立って国民を扇動していった歴史に苦渋の思いを禁じ得ない。しかし、そういう私も戦時中のような時代に生きていたならば、彼らのようになっていたかもしれないとも思う。現在でもあの時代と似たような危険なナショナリズムと排外主義が流行っている。宗教の本質は何か、仏教の核心は何か、そもそも人間も含めて存在とは何なのか、絶えず問い続ける作業が必要のように思う。
修証義の冒頭に、「生を明らめ、死を明らむるは仏家一大事の因縁なり」とある。その原点を忘れないよう、これからも心がけていきたいと思う。

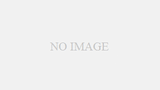
コメント