/ 71.‘真実’という幻想
ダニエル・L・エヴェレットの『ピラハン 「言語本能」を越える文化と世界観』(屋代通代・訳、みすず書房)を読んだ。‘真実’とは何なのか、改めて問い直してくれる一冊である。
著者のエヴェレットは、アマゾンの奥深くに住むピラハンという原住民にアメリカのキリスト教福音派の伝道師として布教しに行ったところが、かえって神への信仰を失って無神論者になった人である。
ピラハンにイエスや聖書の話をした時、ピラハンから‘おまえはイエスを見たことがあるのか? そいつの肌はおれたちのように黒いのか? それともおまえみたいに白いのか? 見たことがないなら、おれたちはその話は信じない。’と言われたという。
ピラハンは直接体験したことしか信じない。彼らの‘信じる’とは‘知る’という。
ピラハンには、神とか天国とか地獄とか罪というような抽象概念とその言葉は存在しない。創世神話もない。あるいは、命をかける‘大義’なるものも認めない。数も色名も左・右の観念もない。小魚2尾が大きい魚1尾と同じ量であることがあるし、また、それよりもっと大きい魚1尾がそれらよりもっと大きい目方のこともあるから、‘1+1=2’が理解しがたい。したがって計算という観念もない。また、黒とは「地はきたない」、白とは「それは見える」または「それはすける」、赤とは「それは火」、緑とは「いまのところ未熟」という。そして、左・右の言葉はなく、その代わりに、「上流の」とか「下流の」とかいうように実在する事物でもって位置を示す。すべてが具象的だということだ。
このように直接体験しか価値を認めない文化において、‘深遠なる真実’とかいう、見ることも触ることもできない観念は無意味だということだ。
「ピラハンにとって真実とは、魚を取ること、カヌーを漕ぐこと、子供たちと笑いあうこと、兄弟を愛すること、マライアで死ぬことだ」。著者のこの言葉は、私にとって「当処を離れず、常に湛然」を身をもって示してくれていると思ったのだった。
ピラハンの社会では、子供も女性も共同体の一人一人が上下なく一人前として扱われ、それぞれが能力に応じて一員としての働きが求められる。男は狩りや漁労に出かけ、ジャングルに入って森を開く。女はジャングルで実を集め、芋を堀り、庭に食糧を集め、時には犬を使って小動物を狩ったり川で魚を釣ったりする。獲得したものはみんなで分け合う。財産はみな平等だ。私有という観念がなく、取ってきたものはその日のうちにみんなで平らげる。蓄えることがないから富という財産もない。
ピラハンの世界では、うつ病などの精神病や慢性疲労とか自殺とか暴力とか無用な不安なるものは存在しないと著者は言う。彼らは世界一幸福だと言えるほど、よく笑う。ピラハンのほがらかな笑いは徹底しているようだ。魚がたくさん取れても笑い、ぜんぜん取れなくても笑う。腹いっぱいでも笑い、空腹でも笑う。風雨が来て家が吹っ飛ぶと、当の本人がもっとも大笑いする。自分の不幸も笑いの種にする。どんな事態になろうと、それに対処する自信があるからだと著者は言う。過去も未来もなく、ただ一日一日を楽しく充実して生きることにしか価値を認めない。ピラハンにとって、精神病や不安や自殺が不思議に思う。彼らには、明治時代に日光の華厳の滝に投身自殺した藤村操の「人生は不可解なり」は存在しないようだ。無論、ピラハンにも生存的不安はある。病気とか死は彼らも怖い。外部からの侵入者や獰猛な爬虫類に警戒する。けれども、それに囚われることなく、現実に前向きに対処しようとする。
「なぜ親は子供をたたくのか?」「アメリカ人やブラジル人はなぜ同朋を殺すのか?」と彼らから聞かれたという。
子供も一人前の人間としてみなされ、自分で対処することを要求される。だから、ピラハンには赤ちゃん言葉がない。なによりも彼らは村の平穏を求める。平穏を甚だしく害した者(たとえば、分けあうという社会規範に反した行為をしたなど)は村から追放されるが罰はない。村の人たちはお互いによく身体的にも触れ合い、会話を楽しむ。村全員がお互いに信じあっている。男女が一緒に生活すれば自動的に結婚となり、別れば自動的に夫婦解消となる。しがらみもなく男女関係は大らかだ。村は核家族が単位となって構成され、その家族間の絆と信頼は強固だ。
日本も含め、先進国といわれる国では、精神病や暴力、無差別殺人、さらに戦争という行いをしたり、しようとしたりしている。私は、エヴェレットの描くピラハンの世界から教えられることは、私たちはいかに頭の中でこねくり回して煩わされているか、ということだ。‘真実’とか‘永遠’とか‘正義’とかなどの抽象概念をあまりにも多く玩んでいることだろうか。自分が見たり体験したりしたことのない情報や話に右往左往し、家族内でもバラバラで人間関係の薄い孤独社会になっているといわれて久しい。家族そろって食事する団らんの風景は珍しくなっているようだ
。 塾から夜遅く帰宅した子供は食卓の上に置いてあるママのメモを見て冷蔵庫から夕食セットを取り出して電子レンジで温めて一人で食べる。パパはさらに遅くなって家族が寝ている頃に帰ってくる。朝は、子供がまだ寝ている間にパパは早く出勤し、子供はそのあとに起きて一人で朝ご飯を食べて学校に行く・・・。こんな家族の風景が当たり前のようだ。
私的所有を前提とする資本主義社会‘自由主義社会はすでに行き詰まっているといわれて久しい。格差拡大と富の偏在はますます進んでいる。アメリカでは上位0.1%が下位90%の富を占有しているといわれる。ピラハンから見れば理解不能だろう。
人類のあるべき姿とは何か? 私たちは一度立ち止まって顧みる必要があるように思う。

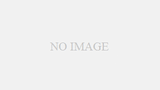
コメント