/ 72.人間の本質は‘我’なのか?
仏教では、人間には‘我’というものがあるから執着心をおこして悪い行いをすると説
いている。‘我’という悪いものが問題をおこしているのだということだ。
なお、ここでいう‘我’は、自分だけよければいいという、「エゴ」の意味で用いている。「諸行無常 諸法無我」にある「我」は永遠不変の凝り固まったものがあるとする固定観念のことをいうが、この「我」の発する元である自己個人に焦点をあてて、自分を絶対視することを‘我’としている。山本リンダではないが、「世界は私のためにある」ということである。
懺悔文には、
「我昔所造諸悪業 皆由無始貪瞋痴 従身口意此所生 一切我今皆懺悔」
とある。現代文に訳せば、
‘私は昔より、たくさんの悪い行いをして悪い報いを作ってきました。これは皆、いつ始まったのかわからないほどはるか以前からある、貪り・怒り・無知蒙昧のためです。身体から出る欲望と口から出る言葉と思う心からこれ(貪瞋痴)が生まれました。私は今、これら一切すべての悪い行いを心底から悔い改めます。’
となるだろうか。
我見我欲にまみれた我利我利亡者の自分のありさまを恥じて、まっとうな人間になりなさいと諭しているといえるだろう。これは、なにも仏教に限ったことではなく、キリスト教やイスラム教など多くの宗教でみられる傾向ではないかと思う。しかし、人は果たして、元から‘悪い’存在だったのだろうか。
前章(『71.‘真実’という幻想』)で触れたピラハンを思った時、人間は元から‘我’というものがあったのではなく、余剰生産を生み出した農耕文明から‘我’が生まれてきたのではないかと思っている。
多くの人類学者たちの、サル・ゴリラ・チンパンジー、今なお存在するさまざまな狩猟採集民族に対する観察と研究によれば、森から草原に出た私たちの祖先は、サルやゴリラ・チンパンジーと違って、獲得した獲物や食糧を集団の皆に平等に分配しあい、一緒に食事してお互いの絆を深め、協力し合って子育てやヒョウなどの獰猛な獣からの脅威に対処したとされる。また、現在の狩猟採集民族でも人類の祖先たちと同様な暮らしをおくり、しかも特筆すべきことは、戦争による殺戮や殺人がめったに見られないということだ。彼らはなによりも村の平穏を求めるということである。戦争は狩猟から起こったという考えが一昔前では定説とされたが、今日ではそれは誤りであることが実証され、戦争はむしろ、1万数千年前ほどに始まった農耕文明によって生じたという見方が有力になっているようだ。
農耕文明は土地の囲い込みを促して、その土地から生み出された食糧はその土地の所有者のものとなるというようにして私有観念が形成されていったようである。そして、生み出された余剰生産物によって、人口増大と富の蓄積とその偏在がもたらされたとみられる。それは、上下関係を作り出して、膨れ上がった集団をまとめるために、また、土地や水などをめぐる争いに対処するために、支配・被支配関係へと発展したと考えられる。その体制を正当化するために、創世神話をはじめとした宗教観念(自然の恵に感謝と願いを込めるアニミズムとは異なる集団統制的なもの。例えばユダヤ教の選民思想やインドのカースト、日本の氏神信仰など)が生まれたと考えられる。この、私有と富の偏在による上下関係の発生が、仏教の問題とする‘我’が現れたのではないかと私は思う。
‘我’なる「エゴ」が貪瞋痴の‘三毒’を生み出して‘苦’という苦悩を抱えてしまったのだと釈尊はいう。そして、そういう‘我’の実体のないことに気づいて、自と他が一枚になった時、「本来の面目」が現れる、即ち、‘我’を離れた本来の人になると教える。
私は、ピラハンや狩猟採集民族の暮らしから思うことは、人間はもともと自然と語り合いながら自然と一体となって生活していたのではないかということだ。無用な不安や苦悩もなく、今ここに生きることをエンジョイしている彼らは、私たちに本当の幸福とは何なのかを示唆しているように思える。
今、世界では相変わらず戦争ないし戦争前夜のきな臭い雰囲気になっている。富の偏在も甚だしく、ごく少数の持てる者と大多数の持てざる者との格差が拡大していると叫ばれている。そして、先進国といわれている地域では孤独と精神病が蔓延し、それに伴って無差別殺人やドラッグ中毒、いじめ、ハラスメントなどが当たり前のように耳にする。ピラハンからこのありさまを目にされたならば、彼らは理解不能とつぶやくに違いない。
このような文明病といってもよいありさまを解決するヒントをピラハンや狩猟採集民族は提示しているように思うのだ。つまり、どれだけたくさん私有するかという勝ち負けの論理ではなく、お互いに尊重し認め合って、助け合うということこそが現代の病を治すのではないかということである。まず、それを家族や二分のまわりから作っていくことだと思う。
ところで、旧統一教会である世界平和統一家庭連合が世界平和の元は家庭だと言っているが、彼らのいう家庭が教祖の方ばかり見ている人間を作っているに過ぎず、家族内の信頼と助け合いがないがしろにされていることを指摘しておきたいと思う。それは家族ではなく、ある特定の個人にすべてを従属させるという、独裁体制に他ならないからである。
また、マルクスは、私有がなく平等であるとする‘原始共産制’を理想として、プロレタリア独裁による共産主義を実現すべきだと主張しているが、彼の見逃した大きな問題があったと私は見る。それは、支配・被支配の上下関係を否定するどころか、より一層の専制体制を作り出してしまったということだ。権力を握る共産党のほんの一部である権力中枢に圧倒的支配力と富の集中がもたらされたという現実となった。大多数の人民は彼らの下僕となってしまった。ある識者は、西洋文明の根幹となっているキリスト教の一神教観念とデカルトの唱える自然と人間の二分論があると指摘している。つまい、ある万能なる個体がすべてを幸せにするという観念と、人間は対立する自然を克服してこそ進歩するという思想である。‘原始共産制’においては、人間は自然の一部として自然と共に生き、上下関係は存在しなかったことが文化人類学で実証されている。それを、マルクスは共‘産主義’に支配・被支配の上下関係をより強固ぽなものとして位置づけてしまったといえるのではないだろうか。
狩りのすぐれた者がより多くの獲物を獲得しても、それを自分や自分の気に入った人だけに独占するのではなく、共同体全員に分け合い、または、その糧を皆で喜び合いながら、上下関係なく、一緒に食べ、喋り、歌い、踊りを楽しみながら親睦を深めあうというピラハンや狩猟採集民族の姿は、人間は本来、共有・共同を宗とし、‘我’とはごど遠い心豊かな存在ではなかったかと教えているように思う。

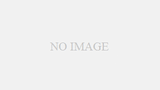
コメント