/ 81.‘存立危機事態’に思う
昨日(2025年11月7日)の国会で、高市新首相は、台湾有事は‘存立危機事態’にあたりうると明確に答弁した。
‘存立危機事態’とは、2015年に制定された安全保障関連法に規定されたもので、日本が直接他国から攻撃されていなくても、日本と密接に関係のある国が他国から攻撃され、それによって日本の存在基盤が否定されかねない多大な損害が想定される場合には集団的自衛権を行使して自衛隊をその国に出動できるというものである。
つまり、高市首相は台湾有事には日本は台湾に自衛隊を出兵して戦争できるというものである。
現在、日本は米国と同様に、台湾とは国交断絶し、中国と国交を結んでいる。「一つの中国」を事実上受け入れて、台湾を中国の一部とみなしていると言われても仕方のない姿勢になっている。これは、中国と国交を結んだ1970年代において、中国が改革開放路線に転じて、それによる中国という巨大マーケットに期待するところが大きかったためだといわれている。事実、日本にとって最大の貿易相手国は輸出輸入ともに中国であり、輸入は2位のアメリカの2倍以上の25%ほどを占める(2021年)。ただし、中国やアメリカにとっては、日本の存在感はまずまず低下して貿易相手国の一つという位置づけになっている(中国にとっての日本は2023年において輸出入ともに4%ほど。アメリカにとっての日本は2024年において輸出では5%、輸入は6%ほどにとどまる)。すなわち、中国やアメリカにとっては日本がおもわしくなっても低レベルの影響にとどまるが、日本にとってはアメリカ、とりわけ中国が風邪を引けば日本は甚大な被害を被るということだ。
いまだにアメリカを凌ぐ経済的影響力を日本に与えている中国という存在の大きさを考えた時、台湾有事では台湾どころではなくなるということだ。日本経済にとって中国は台湾よりはるかにその比重は大きい。日本にとって‘存立危機事態’なのは台湾ではなく、中国だということを認識すべきではないのかと私は思う。
今や日本を遥かに凌ぐ世界第二の経済力と科学技術力を持つ中国は日本をあまり相手にしていない現実を知るべきだろう。中国は巨竜であり、日本はその巨竜に睨まれた蛙みたいなものかもしれない。その弱小な日本が中国にできることは、中国が‘存立危機事態’にならないよう、親日的な中国人をどんどん増やしていくことだと思う。中国にケンカを売るのではなくて、友好関係を作っていこうとすることが‘存立危機事態’を避けるもっとも有効な手段ではないかと思っている。首相である高市氏は台湾以上に中国に向き合う姿勢が弱いように見えてしまうのは、反中国・反ロシアが好きな高市氏のこれまでの姿勢のせいなのだろうか。
また、‘存立危機事態’については、台湾どころか、遠く離れた国にも適用し得るということだ。
かって中東で湾岸戦争があった。原油輸入の9割を占める中東危機に、ホルムズ海峡有事がいわれた。それが今なら、安保法制の‘存立危機事態’によって自衛隊は中東の戦争に出かけて行ったかもしれないということだ。
また、アメリカが始めたアフガン戦争において、今日なら、日本にとって非常に密接なアメリカが大変なことになっているとみなして日本が‘存立危機事態’を発動してアフガニスタンに軍事出動したかもしれないということだ。
私は、‘存立危機事態’について、昭和初頭にあった中国・山東出兵のことが頭に浮かぶ。山東出兵は、1927年から1928年にかけて三次にわたって、時の首相であった対中国強硬外交の田中義一が在留日本人保護を名目に山東に軍事出動したものである。その後、日中十五年戦争につながっていった歴史があった。そのことを考えると、歯止めがきかなくなってしまって泥沼の戦線拡大に陥っていまう危険性を思わずにはいられないのである。今でもウクライナ戦争やイスラエル・ガザ紛争は続いている。
際限のない軍事的危機を避けるためには、‘存立危機事態’は即刻廃止すべきではないかと思う。むしろ、政治的軍事的対立を緩和する国際協調の拠点としての日本の有り方こそが平和国家を自認する日本のあるべき姿ではないかと思う。

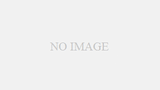
コメント