/ 73.「孤独」ということ
「孤独」という問題が叫ばれて久しい。現代では、それから派生して孤独死とか自殺、無差別殺人ないし殺傷事件、覚醒剤中毒問題がよくニュースに出てくる。さまざまな精神的疾患に悩む人がますます増えているといわれている。それも有名といわれる俳優やタレント、作家、アスリートなどの関係のニュースも珍しくなくなった。
夏目漱石は、『心』や『行人』などの著作で、‘脱亜入欧’の掛け声のなかで現れた個人主義の風潮によって家族や身内・友人にも信じることのできない明治の知識人の深い「孤独」の苦悩を描いている。また、同じ明治期に生きた、東大法科を出ながら破天荒な生活を送った孤独の俳人、尾崎放哉は、「咳をしても一人」という有名な句を残している。
しかし、果たして「孤独」は人間の逃れることのできない宿命なのだろうか。
ゴリラ研究で著名な霊長類学者である山極寿一は『サル化する人間社会』の著作で、とくに家族の崩壊が人間の孤独を生み出していると指摘している。それと同時に、家族がいくつか集まって形成される共同体も壊れてきていると言う。家族とは、共に向き合って食事する間柄であり、見返りを求めない無償の関係であり、子のため、親のため、家族のためとして、えこひいきする関係だという。共同体とは、頂いたらお返しをする、または、差し上げたらお礼がくるという互酬性の関係だという。この、家族という共食関係、共同体という共同関係が壊れていくことによって人間は孤独・孤立して、勝ち負けがすべての「サル社会」に人間社会が劣化していると警鐘を鳴らしている。
人間は集団を離れては生きられない存在だとよくいわれる。赤ちゃんは母親の狭い産道をくぐり抜けるために未成熟な頭の大きさで生まれざるを得ない。そのために運動機能もかなり未熟で、他の動物のように生まれてすぐには立ったり歩いたりできない。まったく無能な存在である。そして、泣きわめくことで母親から離れまいとする。離乳しても、永久歯に生え変わる6歳ごろまでは乳歯という未熟な歯のために大人のようには固い食物は口にできにくい。そのために大人が子供向けの食事を用意しなくてはならない。思春期になって脳はほぼ完成するとされる。結局、生後20年ぐらいかけて脳が完成していくということだ。とにかく人間の子供は手間がかかる。相対的に大きな頭を持った生物の宿命のようである。この問題を解決するために、家族だけでなく、共同体ぐるみで助け合って子供を育ててきたのだといわれる。教育も共同体による子育ての一つといえる。
私たちは大人になっても、人と関わり合って生きている。一人暮らしでも、上下水道や電気ガス、通信などの‘線’と‘管’でつながっている。文化人類学者の関野吉晴はこれを「スパゲティ症候群」と名づけた。ちょうど、重症患者がベッドで点滴・栄養経管・輸血・呼吸器・測定器などの何本もの線と管でつながれて生存を保っているようなものだと形容した。私たちの口にする食べ物でも無数の人の手が関わっている。結局は人間は集団を離れては生きていけない実体がある。にもかかわらず、人は孤独を覚えて不安や憂鬱、さらに場合によっては自らを殺めることがあるのだろうか。かく言う私も修行道場を出て高野山近くの空き家で一人暮らしをしていた30代後半の時、孤独感に襲われて精神的に不安定になったことがあった。ただ、その頃は視力が急激に減退したことも大きかったのだが。
無数の縁のおかげで生きているといわれても、心に安心感を得られず、常に身に鎧を着けているような気分を覚えたことがある。この理由を山極氏のいう家族とあわせて考えてみた時、貸し借りない無償の愛と上下関係なく共に向き合って食事などの団らんをするという場の欠如があるように思う。
家族といわれても、夫は仕事に目いっぱいで疲弊し、妻とはすきま風が吹き、子供は塾や習い事に追い立てられ、もしくはゲームやSNSに夢中になって引きこもりみたいになって、家族そろって食事することもあまりないという風景が広がっているようだ。夫は威厳を保ち、妻は貞節を守って夫に従がい、子は親に従順にして孝行を尽くすというのが本来の家族だと主張する人たちがいる。封建的な上下関係を持った家族観である。しかし、農耕文明以前の石器時代の狩猟採集生活や現在も存在する狩猟採集民の生活の家族をみた時、上下関係なく助け合い支えあって共に生活し、一緒に食事するという家族であると、山極氏や関野氏は言う。気兼ねなく、くつろげる関係が本来の家族のように私は感じる。
まず鎧を脱ぎ捨てて、信頼しあい、共感しあいながら食事を共にする、そういう無償の場作りこそ、人間の帰属意識(アイデンティティー)の元のように思う。安心して身も心も休まることがあれば、「孤独」という疎外感・孤立感は生じることはなく、縁にあって生かされてある喜びを感得できるのではないだろうか。

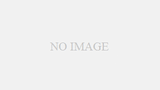
コメント